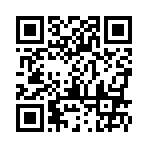› 歯科衛生士23年の経験で患者様を安心させ売上UPするプレゼンテクニック&資料作成術Saeism › 説明媒体&プレゼン資料作成考え方(Saeism) › 資料作成スキル(PowerPoint) › 図形 › プレゼン資料を図解化するということ
› 歯科衛生士23年の経験で患者様を安心させ売上UPするプレゼンテクニック&資料作成術Saeism › 説明媒体&プレゼン資料作成考え方(Saeism) › 資料作成スキル(PowerPoint) › 図形 › プレゼン資料を図解化するということ2019年05月12日
プレゼン資料を図解化するということ
下の資料は実際に企業様で使用されていたプレゼン資料のBeforeと、私がブラッシュアップしたAfterをご了承を得て投稿しております。
sampleでは企業名は伏せさせていただいております。
↓

結構、このBeforeの様な資料、見かけます。
↓
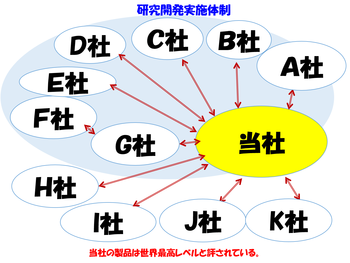
「色々な研究機関に協力いただいて、製品を開発することが出来た。」
「その結果、世界最高レベル製品と評されるようになった。」
この経緯を文章ではなく、しっかりと図解化しようと工夫をされている物です。
資料を図解化することはプレゼンの場面では、非常に重要になってきます。
しかし、この図解化すること自体が結構難しいのですよね。
なぜなら、
その図解化した物が
「聞き手にとって理解しやすい、『聞き手ファースト』の図解化になっている必要があるからです。」
それは、「講師が話したい内容を図解化した物」ではなく、あくまでも
「聞き手にとって理解しやすい図解化に出来ているかどうか?」
が重要になってきます。
ここで再度BeforeとAfterを見てみましょう。
↓

Beforeも図解化しているのですが、Afterは、よりシンプルになっていて、なおかつパッと見て分かりやすくなっていませんか?
Afterのプレゼン資料で使っているテクニックは、
・関係性を正確に示す図解化
・聞き手の目線を意識した図解化
・聞き手の理解を促すアニメーション操作
・配布資料とプレゼン資料の違いを使った図形の使い方
です。
聞き手にとって理解しやすいプレゼン資料「聞き手ファーストの資料」って、結構テクニックが要るもんなのですね。
でも、ここをしっかり抑えると、最終的に「聞き手を動かす」提案力を備えた資料になります。
今日は少し長くなってしまったので、上記の細かいテクニックについてはまた明日投稿しますね(^^)